交通誘導員に資格は必要?保有すべき資格と取得のメリット

「交通誘導員」と聞くと、旗を振って車や人を誘導する姿を思い浮かべるかもしれません。
しかし、交通誘導員は単に誘導するだけではなく、歩行者や運転する方の安全を守る、非常に重要な役割を担っています。
そんな警備の代表ともいえる交通誘導員は資格がなくても働けるのですが、多くの場合、資格保有が求められます。
そこで今回は、交通誘導員の資格についてご紹介します。基本の資格、取得方法、資格取得のメリットなどについても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
交通誘導員は資格なしでもできるが、資格保有が求められるケースが多い
交通誘導員として働く上で資格は必須ではありませんが、資格保有が求められるケースが多々あります。
なぜ資格保有が求められるのか
交通誘導員に資格が求められる理由は、「安全確保のプロであることの証明」と「法律で定められた義務」の2つです。
工事現場やイベント会場など、交通が複雑に入り組む場所では、ちょっとした判断ミスが大きな事故につながりかねません。だからこそ、交通誘導員には高度な専門知識と技能が求められます。
資格を取得する過程では、危険を事前に察知するためのスキルや、状況に応じた最適な合図の出し方・立ち位置、警備に関連する法律知識など多岐にわたる専門スキルを習得します。
これらの知識を持つことで、警備員は単なる指示役ではなく、事故を未然に防ぎ、あらゆる危険から人々を守る「安全のプロ」として機能できるのです。
さらに、高速道路や一部の一般道路での交通誘導業務では、警備業法によって有資格者の配置が義務づけられています。これらの場所での交通誘導がいかに危険を伴い、専門性を要求されるか、という表れでもあるのです。
資格を持つことは法的な義務を果たすだけでなく、より専門的で安全性の高いサービスを提供できるという「信頼の証」にもなります。
交通誘導員が最初に取得する資格は「交通誘導警備業務検定2級」
交通誘導員としてキャリアをスタートさせる際、多くの人がまず目指すのが「交通誘導警備業務検定2級」です。
この国家資格は、交通誘導の現場で働くための基本的な知識と技能を証明する、プロとしての登竜門といえる資格です。18歳以上であれば実務経験がなくても受験できるため、未経験から警備業界に飛び込む人でも挑戦しやすいのが大きな特徴です。
交通誘導警備業務検定2級を取得すれば、一般的な工事現場や商業施設の駐車場など、多様な場所で交通誘導の業務に就くことができます。
加えて、多くの警備会社では資格手当を支給しており、日給や月給に上乗せされることで収入アップに直結することもあります。
この点から、交通誘導警備業務検定2級は交通誘導のプロとして安全を確保し、自身の市場価値を高めるための最初のステップであり、最も重要なステップといえます。
交通誘導警備業務検定の取得方法
「交通誘導警備業務検定」の取得方法は、主に2つです。
1つは、警備業協会などが開催する「特別講習」でしっかり学ぶ方法です。学科と実技の両方を、専門講師からじっくり学びます。
交通誘導の基本ルールから、いざというときの対応、正しい合図の出し方まで、現場で役立つ知識と技術を体系的に習得できます。講師の指導を受けながら実践的に学べるため、合格しやすいのが大きな利点です。
多くの警備会社には、この講習費用を負担してくれる支援制度があるので、入社を検討している会社に確認してみるのも良いでしょう。
もう1つが、自分で勉強して直接試験に挑む方法です。各都道府県の公安委員会が実施する学科試験と実技試験を直接受験するのですが、講習がない分、自分でしっかりと知識と技能を身につける必要があります。
高速道路上の作業では「保全安全管理者」も取得しておきたい資格
「保全安全管理者」は、高速道路での路上作業において、交通規制の計画・実施から作業員の安全管理、危険予知、そして緊急時の対応までを統括する専門家です。
高速道路上での工事やメンテナンス作業は、一般車両が猛スピードで行き交う、非常に危険な環境で行われます。このような場所で事故を未然に防ぎ、作業員と利用者の両方の安全を確保するには、特別な専門知識と管理能力が不可欠。そこで、極めて重要な役割を果たすのが保全安全管理者なのです。
保全安全管理者は、公益財団法人高速道路調査会が実施する講習を修了することで取得できます。高速道路における実務経験年数などの受講要件があるため、気になる方は調べてみてください。
警備のMTでは高速道路警備業務を請け負っており、高速道路の工事やメンテナンスを行う際には交通規制や車両誘導などを行います。一般道路よりも危険が伴いますが、その分やりがいも多い仕事です。興味のある方は、下記よりチェックしてみてください。
警備のMTの高速道路警備業務についてはこちらから
交通誘導員になる前に資格は取得できる?
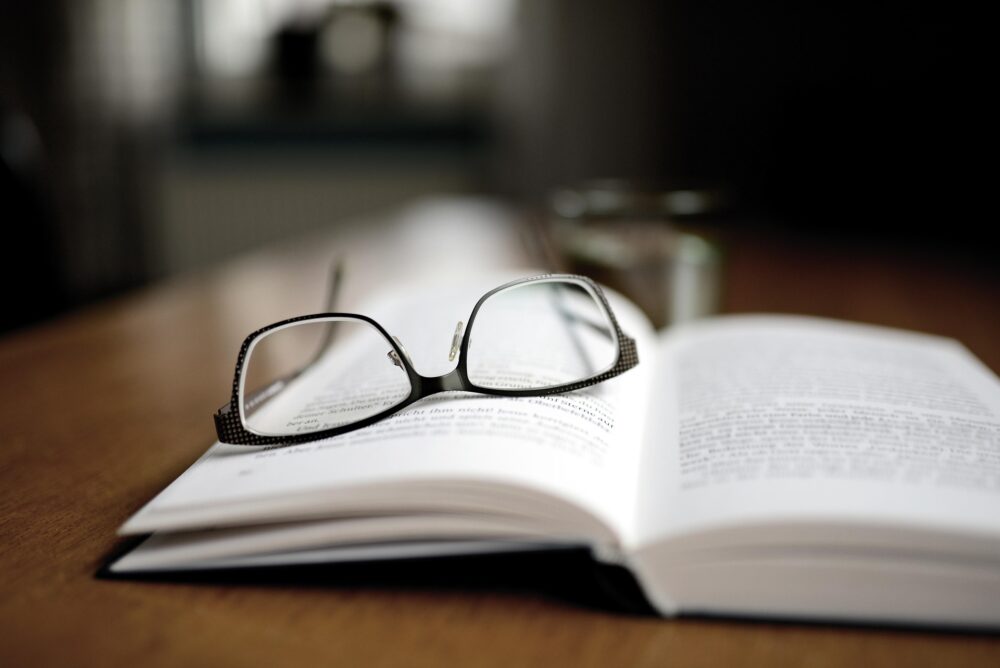
結論からお話しすると、交通誘導員になる前に「交通誘導警備業務検定2級」の資格を取得することは可能です。
現役の警備員じゃなくても資格取得は可能
現役の警備員じゃなくても、交通誘導警備業務検定2級を取得できます。
この資格の大きな特徴は、実務経験がなくても挑戦できる点にあります。「現役の警備員」という肩書きがなくても、意欲さえあれば資格を取得し、警備業界への道を切り拓くことが可能です。
個人で資格を取得する方法
先でも述べたように、交通誘導警備業務検定2級の取得方法は2つあり、特別講習を受講する方法と、公安委員会による直接検定を受験する方法があります。
「警備員になろうとする者の講習」を受ける
「警備員になろうとする者の講習」は、警備員としての経験がない方が特定の警備業務の国家資格(2級)を取得するために受講する特別講習の一種です。
通常の特別講習は、すでに警備会社に所属している警備員を対象としていることが多いですが、「警備員になろうとする者の講習」は、現在警備員ではない一般の方を対象としています。
取得を目指す警備業務の種類(例:交通誘導警備業務2級)によって内容は異なりますが、基本的には「学科講習」と「実技講習」の2部構成になっています。
| 学科講習 | ・警備業法や関連法令に関する知識
・警備業務の基本原則や心構え ・危険予知能力や事故防止に関する知識 ・緊急時の対応方法など |
| 実技講習 | ・警備員としての基本動作(礼式など)
・業務ごとの具体的な技能 └例:交通誘導なら合図の出し方、車両の後進誘導要領など ・負傷者搬送などの実践的なスキル習得 |
講習の最終日に行われる修了考査(学科試験・実技試験)に合格できれば、「講習会修了証明書」の発行、「検定合格証明書」の交付申請を経て、晴れて国家資格である「交通誘導警備業務検定2級」の検定合格証明書が交付されます。
直接検定を受ける
交通誘導警備業務検定2級を、警備会社に所属せず、かつ特別講習を受講せずに個人で取得したい場合は、公安委員会が行う直接検定(通称:直検)を受験します。
独学で直接試験を受けて合格を目指すため、特別講習と比べて合格率は低い傾向にあります。しかし、費用を抑えたい、自分のペースで学びたいという方にとっては、充分に価値のある選択肢となるでしょう。
なお、勉強は市販の参考書などを使って行います。実技試験があるため、実際に体を動かして練習するなどの工夫も必要です。
交通誘導警備業務検定の資格を取得するメリット
こちらでは、交通誘導警備業務検定の資格を取得するメリットについて解説します。
資格手当により給与アップが期待できる
最も分かりやすいメリットが、収入の増加です。
多くの警備会社では、交通誘導警備業務検定の資格を持つ警備員に対して資格手当を支給しています。
警備会社によって金額は異なりますが、日給に数百円〜千円程度が上乗せされたり、月給制の場合でも毎月数千円〜1万円程度の追加支給が見込めたりと、その金額は決して少なくありません。
現場監督など責任ある役職に就ける
交通誘導警備業務検定の資格を持つことは、単に現場での仕事が増えるだけでなく、現場監督など責任ある役職に就けるというキャリアアップの可能性も秘めています。
交通誘導警備業務検定1級の資格は、2級での実務経験を経て取得できる、より上位の国家資格です。1級資格を取得することで、現場の安全管理を担う「保全安全管理者」のような役割を任される他、複数の隊員を束ねる「現場リーダー」、現場全体の責任者である「現場監督」など、より責任のあるポジションへの道が開かれます。
転職に有利になる
交通誘導警備業務検定の資格を持っていれば、警備業界への転職に有利です。
警備会社は常に人材を求めており、とくに専門知識と技能を持つ有資格者のニーズは非常に高いです。交通誘導警備業務検定の資格を持っているということは、採用担当者にとって「基本的な知識を身につけており、すぐに現場で活躍できる可能性が高い」という明確な評価ポイントになります。
また、未経験者であっても即戦力として期待されるため、希望する警備会社への採用がスムーズに進みやすくなります。
警備のMTでは、警備業界で働きたい方を募集しています。警備業務に役立つ資格取得サポートを受けられる他、ベテランのスタッフが指導につくため、未経験の方も安心して学び、キャリアを積むことが可能です。警備業界に興味がある方は、ぜひ一度警備のMTにご連絡ください。
警備のMTに関する詳しい情報はこちらから
交通誘導員が配属される現場とは?

こちらでは、交通誘導員が配属される主な現場をご紹介します。
道路工事現場
道路工事現場では、工事区間での交通規制の設置と管理、工事車両の安全な出入り誘導などを行います。
片側交互通行の誘導や、歩行者の安全な通行路確保など、刻々と変化する状況に対応し、事故を未然に防ぐことが最重要視されます。
建設現場
建設現場では、主に工事車両の安全な出入り誘導と、現場周辺を通行する一般車両や歩行者の安全確保を行います。
大型車両のバック誘導や資材の吊り上げ作業時の交通規制など、危険を伴う作業をサポートしつつ、歩行者や一般道路を走る車両にも細心の注意を払わなくてはなりません。
また、近隣住民への配慮や、工事による騒音・振動に対する細やかな対応も求められることがあります。
駐車場
駐車場での警備業務は、車両のスムーズな入出庫を誘導し、場内での渋滞や接触事故を防ぐことが主な役割です。空きスペースへ誘導する他、歩行者と車両の動線を分けることで、利用者が安心して駐車・移動できるようサポートします。丁寧な接客と、状況に応じた柔軟な対応が求められる場面が多いでしょう。
イベント会場
イベント会場での警備業務は、来場者の安全な入場・退場ルートの確保、混雑箇所の解消、特定の場所への誘導、緊急時の避難誘導などが主な任務です。必要に応じて車両の通行規制も行います。
雑踏警備の要素が強く、人々の動きを予測し、混乱や事故を未然に防ぐための的確な判断力と、ときには冷静な案内が求められます。
まとめ
交通誘導員に必ずしも資格は必要ありませんが、業務上必要な場面が出てくることが予想されるため、多くの警備会社で取得が推奨されています。
警備会社の中には資格取得をサポートしてくれるところもありますし、警備員になる前に資格取得を目指すことも可能です。警備業界への就職・転職を検討している方は、警備に関する資格をチェックしてみてください。
警備のMTは、愛知県名古屋市を拠点に施設警備や交通誘導・雑踏警備などを行う警備会社です。愛知県や岐阜県、北海道に営業所があり、各拠点でさまざまな警備業務を請け負っています。
日程や働く時間などを柔軟に設定でき、未経験でも安心して働ける環境を整えている他、会社契約の寮を完備しているためすぐに腰を据えて働けます。
「警備会社で働きたい」「警備員の仕事に興味がある」という方は、ぜひ警備のMTへご連絡ください。
警備のMTについてはこちらから


